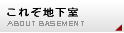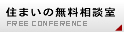�Z�܂��̖������k��
Q. �i�ǂ̒�ƍ|�ǍY��������ꍇ�̌��z���@�ɂ���2010/02/10#2�@�t�r�@�l�@�i�����s�j |
�������i�_��O�j �H�����e ��b ���݃}���V�����iRC�j |
�܂��A�w���\��̓y�n����͂̏�����ƁA���L�̒ʂ�ł��B
�E���Y�̓y�n�͎R�т�4�N�قǑO�ɑ�K�͑������s���J�����ꂽ�����n���̈���ŁA���͂̋��Ɣ�r����ƍł�����Ɉʒu���Ă���B
�E��L�����n�̔̔��v�悪�ŋ߂܂œ�������Ă������߁A����͑�n�������s���������̏�Ԃ̂܂܂ƂȂ��Ă��A���Y�����܂ߑS���Ƃ����݂܂ŏZ��͌��z����Ă��Ȃ��B
�E�w���\��̋��̓쑤�͎s�����L����R�тƗאڂ��Ă���A�R�ё��͍��፷13m�قǂ̉���̎��R�����ƂȂ��Ă���B�������ɂ͖��Ƃ��P�����݂��邪�A�i�ǂ₻�̑��̐l�H�I�ȓy���ߓ��͎{����Ă��Ȃ��B
�E���̖k���͕���6m�̌����ƕ��s�ɐڂ��Ă��邪�A���H�ʂƂ̍��፷����2m���邽�߁A������2m��L�^RC�i�ǂ��ݒu����Ă���
�E���̓����͗��̒��ԏ�ƒʘH�i����������H�ʂƍ��፷�����j������A������������2m��L�^RC�i�ǂ��u�ĂĐڂ��Ă���B
�E���̐�����RC3�K���Ă̘V�l�z�[�����~�n�̋��E�M���M���Ɍ����Ă���B�V�l�z�[�����̕~�n�͂��������1m�قǒႢ���A�V�l�z�[����1F�������ꕔ�n����
���܂锼�n���̂悤�ȏ�ԂŌ����Ă���A���E�ɗi�ǂȂǂ݂͐����Ă��Ȃ��B
�E�O�q��L�^RC�i�ǂ͑������Ɍ��z���ꂽ���̂ŁA�m�F�Ϗƌ����Ϗ��擾���Ă���i����������ݎ����ł��j�B
�E������̗i�ǂ���������i�~�n�̒��S�����j�ɖ�2m���x�L�тĂ���B
��L�̓y�n�ɉ����ʐ�40�A�����ʐ�20�ؒ��x��2�K���Ėؑ�2X4�Z������z���������߁A����n�E�X���[�J�[�i�����Ёj�ɑ��k�����Ƃ���A���L�̂悤�Ȑ������܂����B
���Y�n��̌��z�m�F��S�����錧�̓y�؎������Ɂi�����Ђ̕����j�m�F�����Ƃ���ɂ��ƁA�u��n�ʂ̈ꕔ���쑤�̂���������35�x�̊p�x�ň����������p��������Ɉʒu���Ă���\��������A�����p�̎ΐ���������Ɉʒu����̈�Ɋ�b��z�u����ꍇ�ɂ́A�|�ǍY���g�p�����n�Չ��ǂ��s���A�Y�̉��[�������p�̎ΐ���艺�܂œ͂��悤�v����K�v������v�Ƃ̌������Ƃ̂��Ƃł����B
���̌�F�Ђ��|�ǍY�̑Ő݂ɂ��Č����������ʁA�����p�̖����N���A����ɂ͍ł��������̕����Ő[��5m�܂ōY��Ő݂���K�v������ƂƂ��ɁA�Y�͂������̈ꕔ�������łȂ��x�^��b�̑S�̂ɔz�u���Ȃ���Ȃ炸�A���v�悵�Ă���Ԏ��ł͑��40�{�قǂ̍Y��z�u����K�v������A���̔�p�͖�100���~���x������Ƃ̂��Ƃł����B
�܂��A�����_�ł͒n�Ւ��������Ă��Ȃ��i�K�̂��߁A�������Ȓn�Ղł���Ύx���w�܂ōY��łK�v������̂ŁA���̏ꍇ�ɂ͍Y�̒�����5m�ł͑��肸�lj��̔�p����������\��������Ƃ̂��Ƃł����B
����ɗ\��̊Ԏ��ł́A�����̔z�u���k���Ɠ����̗i�ǂ�1m�O��܂Őڋ߂��邱�Ƃ������ꂸ�A�O�q��L�^RC�i�ǂ̒����2m�قǓ����i�~�n�̒��S�����j�ɐL�тĂ��邱�Ƃ���A�i�ǂ�2m�ȓ��Ɍ�����z�u���悤�Ƃ���ƃx�^��b�̈ꕔ����̏���ɏd�Ȃ邽�߁A���̕����̍Y�͗i�ǂ̒�Ɋ����Ȃ��ʒu�ɂ��炵�Ĕz�u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Ƃ��Ƃł����B
�����i�Ǒ��̊�b�̊O�������ɍY��łĂȂ��ꍇ�ɂ́A�d�̃o�����X���l�����Ċ�b��⋭�����v�Ƃ���K�v������A����ɒlj��̔�p����������Ƃ̂��Ƃł����B
�������A����������Ċ�b����̏���ɏ��Ȃ��悤�Ȍ����̔z�u�ɂ��悤�Ƃ���ƁA���Ȃ苷���ȏZ������Ă��Ȃ����߁A���̂悤�Ȍ��ĕ��ȊO�ɑI���̗]�n������܂���B
���Ƃ��Ă͗i�Ǒ��̊�b�̊O�����i��1m���x�j�ɂ͍Y��z�u�ł����A��b�̕⋭�ɂ���ĉd���x����Ƃ����\�����{���ɑ��v�Ȃ̂��������炸�A���S���⌚�z��p�̊ϓ_�ŕs���������Ă��܂��B
�������܂����A���L�̎���ɃR�����g������K���ł��B
����P�F��L�̂悤�ȏZ��̌��z���@�͓K������ʓI�i�������Ȃ��j���H
�˗ǐS�I�ȋƎ҂ł���Έ����Ȃ��悤�Ȗ����ȓ��e�ł͂Ȃ����H
����Q�F��L�̌��z���@�ɋN�����Ĕ���Ȓlj���p����������댯���͂Ȃ����H
�˂��Ƃ��Ηi�ǂ̂�蒼���Ȃ�
����R�F���S���ɖ��͂Ȃ����H
�˕s�������̉\�������������܂�Ȃ�
�Ō�ɗi�ǂ̐}�ʂɋL�ڂ���Ă����X�y�b�N���L�ڂ��Ă����܂��B
���A3�Ԗڂ́u�tLRC1.0m�v�͌�����z�u����Ȉʒu�ɂ̂ݎg�p����Ă���A����̒��Ɋ�b�������邱�Ƃ͂���܂���B
��L�^RC2.5m�i�����jL-S2.5(C) 100
����
�P�D�n�ϗ́@100kN/���Ĉȏ�
�Q�D�w�ʓy���@�������C�p30�x�@�S����0kN/���ā@�y�̎��ʒP��18kN/�������[�g
��
�R�D�x���n�Ձ@�������C�p30�x�@�S����0kN/����
�S�D�����E�͓��a75mm�ȏ�̉��r�ǂ��̑�����ɗނ���ϐ��ޗ���p�������̂ŁA
3���ē�����1�����ȏ�݂��邱�ƁB
�T�D�S�̋��e�����͓x�@200N/m���Ĉȏ�
�U�D�S�R���N���[�g��4�T���k���x�@21N/m���Ĉȏ�
�V�D��ډd�@10kN/���Ĉȏ�
��L�^RC2.0m�i�����jL-S2.0(C) 100
�����@��L��L�^RC2.5m�Ɠ���
���tLRC1.0mTYPE�i���[���j�tL-R1.0
����
�P�D�n�ϗ́@30kN/���Ĉȏ�
�Q�D�������C�p20�x�i�w�ʓy�j�@
�R�D�y�̒P�ʎ���16kN/�������[�g��
�S�D�����E�͓��a75mm�ȏ�̉��r�ǂ��̑�����ɗނ���ϐ��ޗ���p�������̂ŁA
3���ē�����1�����ȏ�݂��邱�ƁB
�T�D�S�̋��e�����͓x�@200N/m���Ĉȏ�
�U�D�S�R���N���[�g��4�T���k���x�@21N/m���Ĉȏ�
�X�������肢�v���܂��B

> ���ݒ����Z��̌��z�p�n�Ƃ��čw�����l���Ă���y�n�ɂ��āA�n
> �E�X���[�J�[�����Ă���Ă��錚�z���@�ɕs���������Ă���A��
> ��ƂƂ��Ă̂��ӌ����f���������₢���킹�������Ă��������܂�
> ���B
> �܂��A�w���\��̓y�n����͂̏�����ƁA���L�̒ʂ�ł�
> �B
> �E���Y�̓y�n�͎R�т�4�N�قǑO�ɑ�K�͑������s���J�����ꂽ��
> ���n���̈���ŁA���͂̋��Ɣ�r����ƍł�����Ɉʒu���Ă�
> ��B
> �E��L�����n�̔̔��v�悪�ŋ߂܂œ�������Ă������߁A����͑�
> �n�������s���������̏�Ԃ̂܂܂ƂȂ��Ă��A���Y�����܂ߑS��
> ��Ƃ����݂܂ŏZ��͌��z����Ă��Ȃ��B
> �E�w���\��̋��̓쑤�͎s�����L����R�тƗאڂ��Ă���A�R��
> ���͍��፷13m�قǂ̉���̎��R�����ƂȂ��Ă���B�������ɂ͖�
> �Ƃ��P�����݂��邪�A�i�ǂ₻�̑��̐l�H�I�ȓy���ߓ��͎{�����
> ���Ȃ��B
> �E���̖k���͕���6m�̌����ƕ��s�ɐڂ��Ă��邪�A���H�ʂƂ̍�
> �፷����2m���邽�߁A������2m��L�^RC�i�ǂ��ݒu����Ă���
> �E���̓����͗��̒��ԏ�ƒʘH�i����������H�ʂƍ��፷��
> ���j������A������������2m��L�^RC�i�ǂ��u�ĂĐڂ��Ă���B
> �E���̐�����RC3�K���Ă̘V�l�z�[�����~�n�̋��E�M���M���Ɍ�
> ���Ă���B�V�l�z�[�����̕~�n�͂��������1m�قǒႢ���A�V�l
> �z�[����1F�������ꕔ�n����
> ���܂锼�n���̂悤�ȏ�ԂŌ����Ă���A���E�ɗi�ǂȂǂ݂͐���
> ��Ă��Ȃ��B
> �E�O�q��L�^RC�i�ǂ͑������Ɍ��z���ꂽ���̂ŁA�m�F�Ϗƌ���
> �Ϗ��擾���Ă���i����������ݎ����ł��j�B
> �E������̗i�ǂ���������i�~�n�̒��S�����j�ɖ�2m���x�L�т�
> ����B
> ��L�̓y�n�ɉ����ʐ�40�A�����ʐ�20�ؒ��x��2�K���Ėؑ�2X4�Z
> ������z���������߁A����n�E�X���[�J�[�i�����Ёj�ɑ��k�����Ƃ�
> ��A���L�̂悤�Ȑ������܂����B
> ���Y�n��̌��z�m�F��S�����錧�̓y�؎������Ɂi�����Ђ̕����j�m
> �F�����Ƃ���ɂ��ƁA�u��n�ʂ̈ꕔ���쑤�̂���������35�x��
> �p�x�ň����������p��������Ɉʒu���Ă���\��������A����
> �p�̎ΐ���������Ɉʒu����̈�Ɋ�b��z�u����ꍇ�ɂ́A�|
> �ǍY���g�p�����n�Չ��ǂ��s���A�Y�̉��[�������p�̎ΐ���艺��
> �œ͂��悤�v����K�v������v�Ƃ̌������Ƃ̂��Ƃł����B
> ���̌�F�Ђ��|�ǍY�̑Ő݂ɂ��Č����������ʁA�����p�̖���
> �N���A����ɂ͍ł��������̕����Ő[��5m�܂ōY��Ő݂���K�v��
> ����ƂƂ��ɁA�Y�͂������̈ꕔ�������łȂ��x�^��b�̑S�̂�
> �z�u���Ȃ���Ȃ炸�A���v�悵�Ă���Ԏ��ł͑��40�{�ق�
> �̍Y��z�u����K�v������A���̔�p�͖�100���~���x������Ƃ�
> ���Ƃł����B
> �܂��A�����_�ł͒n�Ւ��������Ă��Ȃ��i�K�̂��߁A�������Ȓn
> �Ղł���Ύx���w�܂ōY��łK�v������̂ŁA���̏ꍇ�ɂ͍Y��
> ������5m�ł͑��肸�lj��̔�p����������\��������Ƃ̂��Ƃ�
> �����B
> ����ɗ\��̊Ԏ��ł́A�����̔z�u���k���Ɠ����̗i�ǂ�1m�O��
> �܂Őڋ߂��邱�Ƃ������ꂸ�A�O�q��L�^RC�i�ǂ̒����2m��
> �Ǔ����i�~�n�̒��S�����j�ɐL�тĂ��邱�Ƃ���A�i�ǂ�2m�ȓ���
> ������z�u���悤�Ƃ���ƃx�^��b�̈ꕔ����̏���ɏd�Ȃ邽
> �߁A���̕����̍Y�͗i�ǂ̒�Ɋ����Ȃ��ʒu�ɂ��炵�Ĕz�u��
> �Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Ƃ��Ƃł����B
> �����i�Ǒ��̊�b�̊O�������ɍY��łĂȂ��ꍇ�ɂ́A�d�̃o��
> ���X���l�����Ċ�b��⋭�����v�Ƃ���K�v������A����ɒlj�
> �̔�p����������Ƃ̂��Ƃł����B
> �������A����������Ċ�b����̏���ɏ��Ȃ��悤�Ȍ����̔z
> �u�ɂ��悤�Ƃ���ƁA���Ȃ苷���ȏZ������Ă��Ȃ����߁A��
> �̂悤�Ȍ��ĕ��ȊO�ɑI���̗]�n������܂���B
> ���Ƃ��Ă͗i�Ǒ��̊�b�̊O�����i��1m���x�j�ɂ͍Y��z�u�ł���
> �A��b�̕⋭�ɂ���ĉd���x����Ƃ����\�����{���ɑ��v�Ȃ�
> ���������炸�A���S���⌚�z��p�̊ϓ_�ŕs���������Ă��܂��B
> �������܂����A���L�̎���ɃR�����g������K���ł��B
> ����P�F��L�̂悤�ȏZ��̌��z���@�͓K������ʓI�i��������
> ���j���H
> �˗ǐS�I�ȋƎ҂ł���Έ����Ȃ��悤�Ȗ����ȓ��e�ł͂Ȃ���
> �H
> ����Q�F��L�̌��z���@�ɋN�����Ĕ���Ȓlj���p����������댯
> ���͂Ȃ����H
> �˂��Ƃ��Ηi�ǂ̂�蒼���Ȃ�
> ����R�F���S���ɖ��͂Ȃ����H
> �˕s�������̉\�������������܂�Ȃ�
> �Ō�ɗi�ǂ̐}�ʂɋL�ڂ���Ă����X�y�b�N���L�ڂ��Ă����܂��B
> ���A3�Ԗڂ́u�tLRC1.0m�v�͌�����z�u����Ȉʒu�ɂ̂ݎg�p����
> �Ă���A����̒��Ɋ�b�������邱�Ƃ͂���܂���B
> ��L�^RC2.5m�i�����jL-S2.5(C) 100
> ����
> �P�D�n�ϗ́@100kN/���Ĉȏ�
> �Q�D�w�ʓy���@�������C�p30�x�@�S����0kN/���ā@�y�̎��ʒP��18
> kN/�������[�g
> ��
> �R�D�x���n�Ձ@�������C�p30�x�@�S����0kN/����
> �S�D�����E�͓��a75mm�ȏ�̉��r�ǂ��̑�����ɗނ���ϐ��ޗ���
> �p�������̂ŁA
> 3���ē�����1�����ȏ�݂��邱�ƁB
> �T�D�S�̋��e�����͓x�@200N/m���Ĉȏ�
> �U�D�S�R���N���[�g��4�T���k���x�@21N/m���Ĉȏ�
> �V�D��ډd�@10kN/���Ĉȏ�
> ��L�^RC2.0m�i�����jL-S2.0(C) 100
> �����@��L��L�^RC2.5m�Ɠ���
> ���tLRC1.0mTYPE�i���[���j�tL-R1.0
> ����
> �P�D�n�ϗ́@30kN/���Ĉȏ�
> �Q�D�������C�p20�x�i�w�ʓy�j�@
> �R�D�y�̒P�ʎ���16kN/�������[�g��
> �S�D�����E�͓��a75mm�ȏ�̉��r�ǂ��̑�����ɗނ���ϐ��ޗ���
> �p�������̂ŁA
> 3���ē�����1�����ȏ�݂��邱�ƁB
> �T�D�S�̋��e�����͓x�@200N/m���Ĉȏ�
> �U�D�S�R���N���[�g��4�T���k���x�@21N/m���Ĉȏ�
> �X�������肢�v���܂��B
> ����P�F��L�̂悤�ȏZ��̌��z���@�͓K������ʓI�i�������Ȃ��j���H
> �˗ǐS�I�ȋƎ҂ł���Έ����Ȃ��悤�Ȗ����ȓ��e�ł͂Ȃ����H
����āA�Y��i�Y�̍ʼn��[�j�͂��̂R�O�x���C���̉��i��肳��ɂP�����x�[���j�܂ŐL���˂Ȃ�܂���B
�����ŁA�����Ђ̌������Ă���Y�͒n�Չ��ǍY�̉\��������܂��̂ł��m�F���������B
�̗p�\��̍|�ǍY����b�Y�i�n���ׂ�����ɑR���A�������d���x���邱�Ƃ��ړI�Ƃ����Y�j�Ƃ��đI�肵�Ă���n�j�ł��B�O�q�̒n�Չ��ǍY�i�����d�݂̂��x����ړI�̍Y�j�͖ړI���قȂ�܂��̂ŗ��ӂ��Ă��������B
�S�O�{�łP�O�O���~���P�{�Q�T�O�O�O�~�Ƃ͒n�Չ��ǍY�̉\�����Z���ł��B�i�n�E�X���[�J�[�Ȃ�����ł���̂�������܂��E�E�E�B�j
> ����Q�F��L�̌��z���@�ɋN�����Ĕ���Ȓlj���p����������댯���͂Ȃ����H
> �˂��Ƃ��Ηi�ǂ̂�蒼���Ȃ�
�n�Ւ����݂̂Ȃ炸�{�[�����O�n���������K�{�Ǝv���܂��B
���̌��ʂ���ӊ��Ȃǂɂ���čH�����@���ς��܂��̂Œlj���p�Ȃǂ͖{�����[�����e�����ł͔��f���t���܂���B
��{�I�ɂ͈��肵���n�Ղ̊m�ۂƃV�b�J��������b�̐v���d�v�Ɣ��f����܂��B
�i����̂̓n�E�X���[�J�[�Ȃ̂Ŗ���ɂ܂Ƃ߂��邩������܂��n�Ղ��b�Ȃǂ̉����̂͂ǂ��ł��傤���H�j
> ����R�F���S���ɖ��͂Ȃ����H
> �˕s�������̉\�������������܂�Ȃ�
�Q�̓��e�Əd�����܂�����肪�N���Ȃ��悤�ɂ���̂��v�Ȃ̂ł��B
�H������H�@�ɂ���ĕς��܂��̂ōH�@�̑I��Ɛv�͈�̂ōl�����˂Ȃ�܂���B
�n�ՁA��b�A����̂��̑��̂��ꂼ������Ȃ���S�̂�v���邱�Ƃ����߂��܂��B
�u���S���m�ۂ��邽�߂ɂǂ̂悤�Ȋe���v�Ȃ�тɑS�̐v�����邩�v���d�v�ł��B
�֑��Ȃ���A
�O�Ȉ�͊��҂���̏Ǐ犳���𐄒肵�A�e��̌����f�[�^���炢�낢��ȏ���ǂݎ��Ȃ��犳���̈ʒu����肵�āA�{�p�ɕK�v�Ȑ�����W�߂Ĉӌ����A�����Ɍ������{�p���j�����߂܂��B�����v�Ƃ����܂��B�v�Ɋ�Â��Ė��S�������đ����Ɍ����{�p���܂��B���ꂪ��p�ł��B
���z�v�҂����������O�Ȉ�Ɠ����ŁA���낢��Ȓ����f�[�^����őP��͉��������o���Ă����܂��B�i�����v�Ƃ����܂��B�j
�M�@���i�N�I�Ɍ��������邱�Ƃ́A�n�Ղ݂̂Ȃ炸��b�����̂��̑��ɂ��đ��ʓI�Ȍ����i�v�j�����邱�Ƃɂ���Ċm�ۂ���܂��B
����āA���S���̖��A�@�\���̖��A�i�����i�ϋv���j�̖��A�o�ϐ��̖��A�ӏ����̖��A�R�X�g�R���g���[���i�H����j�Ȃǂ͂��ׂĐv�҂̔\�͂ɂ��܂��B
�M�@�S�������̉c�ƃ}���̔\�͂ɂ��Ƃ��������܂����A�v�҂͉c�ƃ}���ȏ�̔\�͂�L���Ă��邱�Ƃ��厖�ŁA�c�ƃ}���������̐v�҂̔\�͂̌��ɂ߂��ł��d�v�ł��B